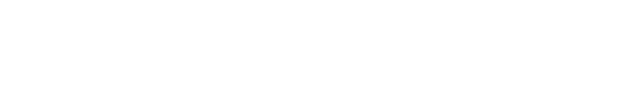施設案内
CT
CT(Computed Tomography)検査とはなんなのか、それを簡単に説明します。
CTはドーナツ型の輪っかのなかに患者さんが入り360度からX線(放射線の一種)をあてることで画像を撮影します。
体の構造物(骨や肺や脳など)によってX線の通過のしやすさが違うので、それがコントラストになって体の内部が写真のようにうつしだせるわけです。
昔は一方向からX線をあてて写真をとる(これがいわゆるレントゲン検査ですね)ことしかできなかったんですが、これを輪っかにして高速回転させて体のいろんな角度からX線をあてることで、より正確な写真がうつせるようになりました。
しかし、もちろんいろんな角度からX線をあてるということは放射線に被ばくしてしまう量も増えるということです。
当院では少しでも被ばく量を減少させるために最新のCT検査機器『Supria Optica』を採用しています。
被ばく量は従来のものよりも83%程度カットできるとのことです。皆さんももし検査が必要であった場合、なるべく被ばく量を抑えた 最新の検査機器で検査を受けることをお勧めします。
この投稿をInstagramで見る
MRI検査
MRI検査とはmagnetic resonance imagingの略ですごく簡単に言うと、強力な磁力の力で体の水素原子の核にわずかな運動をおこし、磁力を中止したあとにその原子がもとに戻る時間を計算して画像化する検査になります。細かいことを言うと物理学の話になるので割愛させていただきますが、結局は強力な磁力の力を利用するので、体に金属があると検査できない場合があります。
現在の医療用の金属は大半が「チタン」という、非磁性体つまり磁力を帯びない金属で作られているので大抵の場合検査ができます。注意点としてはペースメーカーなどの場合は検査を受けることは可能なのですが、強力な磁場の力で設定が狂ってしまう場合があるので、ちゃんと設定ができる医療機関でないとMRI検査を受けることができません。また市販の金属などはチタンでできていないものが大半と思いますので検査室の持ち込みは「厳禁」となります。
MRI検査は強力な装置なので熱を帯びやすくをそれを冷やすために「ヘリウム」という気体を用いて冷やしていたのが一般的でした。しかし、ヘリウムも天然ガスから抽出するので生産量に限りがあり資源の問題が訪れています。
当院のMRI装置はヘリウムを用いない最新のMRI検査機器であり、環境にも優しい製品になっています。
また最新のAI画像処理システムを搭載しており、なるべく検査時間が短く患者さまにも負担が少ないようなシステムになっています。
この投稿をInstagramで見る